数学の魅力
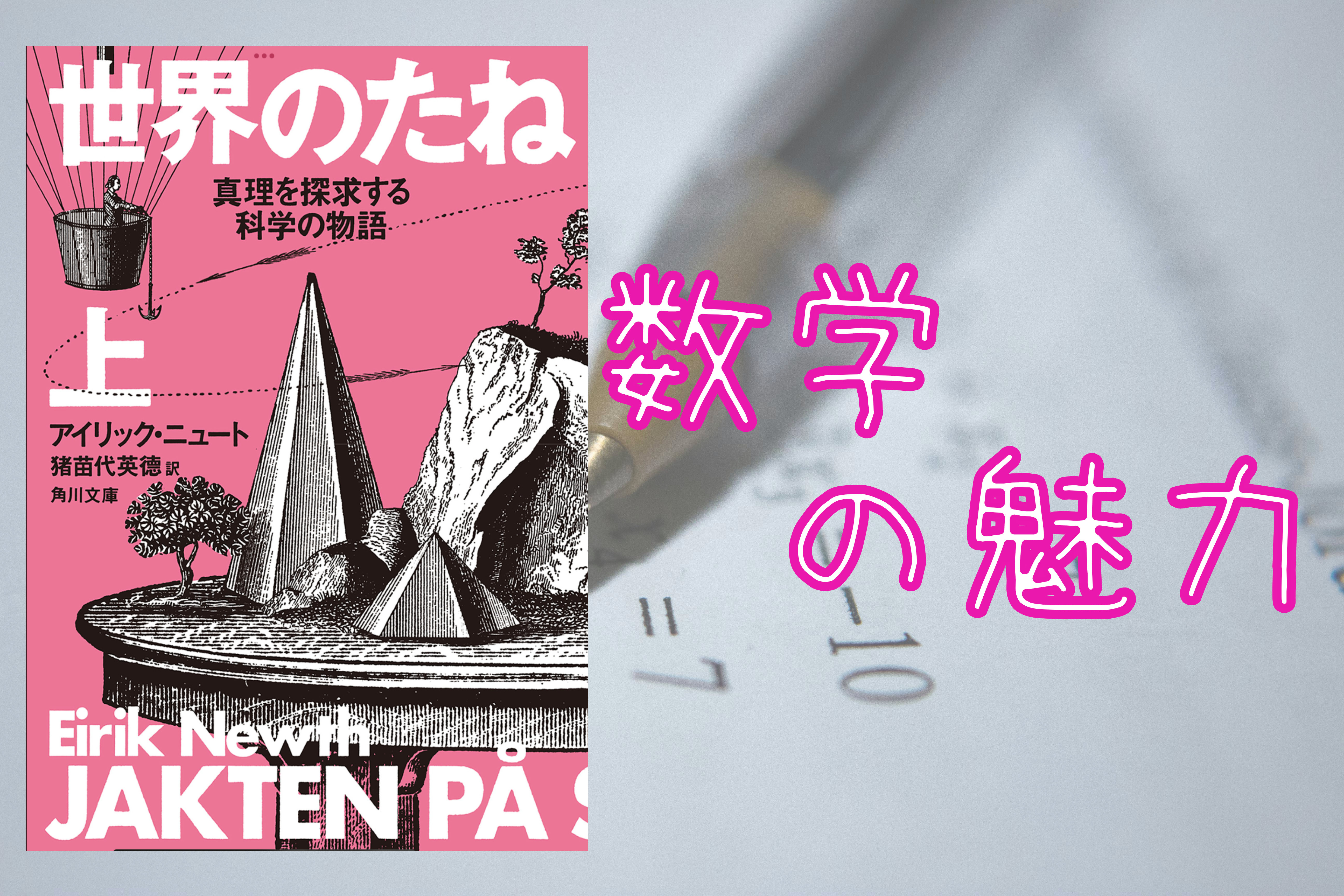
『世界のたね 真理を探求する科学の物語』は、科学の歴史や探求の面白さをわかりやすく伝える一冊です。
本書の「数の魅力」の章では数学がどのように誕生し、発展してきたのかを語っています。
今回は、その内容をかみ砕いて紹介します。
なぜ数学は難しいのか?
「数学が苦手」と感じる人は多いですが、それは人間の脳が計算に向いていないからです。
原始時代の人々にとって重要なのは、生き延びること。
計算よりも、危険を察知する力や、食料を見つける能力のほうが必要でした。
そのため、数を直感的に理解できる範囲は限られており、5~6個を超えると認識しづらくなると言われています。(机の上に缶ジュース7個をイメージしてみてください)
数学の始まり ー シュメール人とバビロニア人
では、そんな人間がなぜ数学を発展させたのでしょうか?
約5000年前、シュメール人が大都市を作り始めた頃、税の計算や商業、土木工事のために数学が生まれました。
さらに、バビロニア人はその知識を発展させ、天文学と結びつけました。
彼らは星の動きを計算し、暦を作成することで、未来を予測できると考えたのです。
ピュタゴラスと「数の神秘」
数学の発展に大きく貢献したのが、古代ギリシャの哲学者ピュタゴラスです。
彼は、三角形の辺の長さに関する「ピュタゴラスの定理」を確立し、さらに音楽と数学の関係を発見しました。
「美しい音の背後には数がある」と考えた彼は、数学を神聖視し、数を信仰の対象にする教団まで作り上げました。(この教団は少し恐ろしい教団なんですが・・・)
数学を学ぶ理由
本書は、「数学ができると得だから」という実用的な理由だけでなく、「自然界は数学で表せる」という本質的な理由を提示します。
たとえば、星の動きや音楽の調和など、数学はあらゆる現象に深く関わっており、それを理解することで世界をより深く知ることができるのです。
まとめ
本書では、数学の起源からその発展、さらには「数学がなぜ重要なのか?」まで、わかりやすく解説されています。
数学に苦手意識がある人でも、歴史やエピソードを交えながら楽しく学べる内容です。
「数学って面白いかも?」と思えたら、ぜひ本書を手に取ってみてください!
