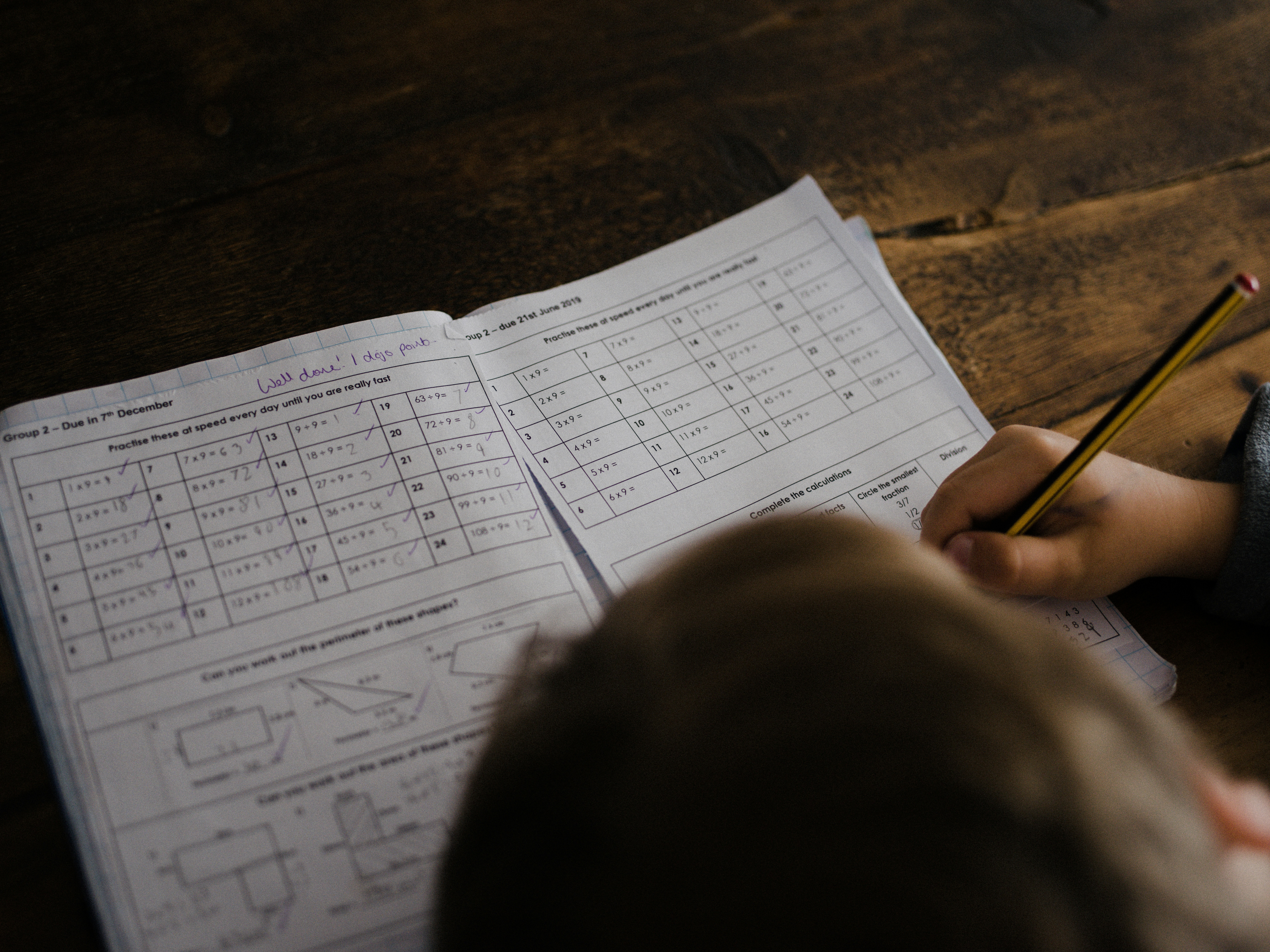高校は義務教育じゃないよね?


高校における成績の付け方に関する考察をしていくよ!
現在の日本の高校教育は、実質的に「義務教育化」しているのではないかと感じます。
具体的に言うと、成績における「未習得」(5段階評価での「1」)をつけることを極端に避ける傾向があるのです。
これは教育の質を考えたときに、非常に由々しき事態であると言えるでしょう。
「未習得」を避ける傾向とその背景
成績評価において「未習得」をつけることが避けられる背景には、いくつかの要因が考えられます。
教科担当者の指導不足と捉えられる
生徒に「1」をつけることは、教員自身の指導力不足と見なされる可能性があります。
担任や教科担当者の負担が増える
未習得の生徒に対しては、保護者の呼び出しや補習対応など、担任および教科担当者の業務が増加します。
追認考査の負担
翌年度に追認考査を受けさせる必要が出ることで、教科担当者にさらなる負担がかかります。
以上の結果、成績が芳しくない生徒に対して「特別課題」などの加点材料を個別に与え、最後の成績で加点するという対応が行われるケースも少なくありません。
「無理やり修得」による問題点
知識が十分に修得されていない生徒を無理やり修得扱いにすることで、以下のような問題が生じます。
学習意欲の低下
生徒が「適当にやっても単位を取ることができる」と油断し、真剣に学習しなくなる可能性があります。
学校の評判低下
卒業生の知識量が低くなることで、その学校全体の教育レベルが疑問視され、評判を下げることにつながります。
不公平な評価
特別課題」を与えられる生徒とそうでない生徒の間に実質的な不公平が生じ、成績評価の公平性が損なわれます。
また、これは個人的な感情ですが、自分が教えている生徒の知識量が不足しているにもかかわらず修得扱いになることに対して、教師として無力感を覚えることはないのでしょうか。
改善策の提案
こうした現状を改善するためには、次のような取り組みが必要です。
公平な成績評価の徹底
年度初めに決めた成績の付け方を貫き、「特別課題」などの加点制度を廃止し、公平かつ一貫した評価を行う。
教員の業務負担軽減
未習得の生徒が出た際の保護者呼び出しや追認考査などの業務を見直し、教員の負担を減らす仕組みを作る。
教員の意識改革
教員が自らの授業に誇りを持ち、成績評価を正確かつ責任を持って行う姿勢を育む。
明確な評価基準の設定
成績の付け方に曖昧さをなくし、生徒や保護者に対してもきちんと説明できる明確な基準を設ける。
まとめ
日本の高校教育における「未習得」を避ける傾向は教育の質の低下を招く大きな問題です。
成績評価の公平性と正確性を保つためには、教員が自身の指導力に誇りを持ち、一貫した評価基準を貫く姿勢が求められます。
教育の本質を見失わず、生徒が真に必要な知識と能力を身につけられるよう、今一度、成績評価の在り方を見直す必要があるのではないでしょうか。